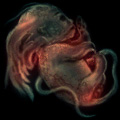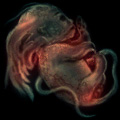
11.精神(こころ)を喰うもの
「黒神さんっ! あれをっ!」
神代先生が「願いをかなえるアクセ」を指さした。
ほとんど同時に、黒神由貴が手に持った紙切れをアクセにかぶせた。
「え!?」
黒神由貴が小さく声を上げた。
アクセにかぶせた紙切れ──つまり呪符から、煙が上がっていた。
アクセの部分が、黒く焦げ始め、いぶっていた。
呪符が、黒神由貴の呪符が、負けている……のか?
「黒神さんっ! どいてっ!」
神代先生が叫んで、手に持った道具を呪符に突き立てた。
ビヂャッ!
そんな音を立てて、突き立てた道具のあたりを中心にして、呪符の下から真っ赤な血がしぶいた。
神代先生が突き立てた道具を抜くと、抜いた穴からも、さらに血が上方にしぶいた。
黒神由貴が、血にまみれた呪符を取る。
何もなかった。
アクセが消えていた。
「何バカなことやってるのっ!」
神代先生が怒鳴った。
「あんたたち、自分がどんな危険なことしていたか、わかってるのっ!」
そして、私を振り向いて、
「榊さんっ、あなたがいて、なんでこんなバカなことをさせるのっ!」
「すみませんっ」
神代先生のあまりの剣幕に、頭を下げるしかなかった。
「誰がこんなことをやろうとしたのっ! 誰がこれを持ってきたのっ!」
先生が言う「これ」というのが、「願いがかなうアクセ」のことであるのは、すぐにわかった。
私や大坪ミキたちは、ブースを見回して、マオタイギの姿を探した。
マオタイギは、私たちから少し離れたところに立っていた。
マオタイギの姿を見た大坪ミキたちが、悲鳴を上げた。
マオタイギの腹部に、穴が開いていた。
血も内臓も、見えない。
ただ、ぽっかりと穴が開いていた。
何かの冗談としか思えなかった。
マオタイギは、憎悪のこもった目で、私たちを──おそらくは、正確には、黒神由貴と神代先生をにらみつけていた。
「くちおしや……」
マオタイギが言った。
「よもや陰陽師などというやつばらが出でようとは、思いもよらなんだわ。この恨み、いつか必ず晴らしてくりょうぞ」
そう言うと、マオタイギの身体が崩れ始めた。
なんと言えばいいか、ストーブの近くに置いた蝋人形が溶けていくように、グニャグニャと歪んで縮み始めたのだ。
「逃がすかっ!」
神代先生が叫んで、道具を投げつけた。
だが道具が突き刺さるよりも、縮んでいく速度の方が早く、道具は壁に突き刺さり、縮んでいったマオタイギは、床に痕跡だけが残る状態になって、消えた。
「ちっ」
神代先生は舌打ちすると、壁に突き刺さった道具を引き抜いた。
振り向いて、私たちをにらみつける。
「今のはね、人の魂を喰う化け物なのよ。それも、恐怖の絶頂にある状態の魂が大好物でね。あんたたち、あいつに喰われるところだったのよ」
「今の──誰──っと、なんだったんですか」
私は言った。
大坪ミキや他の子たちは抱き合って震え、口もきけない状態だった。
「魂呑鬼──中国名は、マオタイギ」
私は目をむいた。マオタイギ自身が、そう名乗っていた。
「もともとは誰かを呪うために作られた呪物。道具よ。仔をはらんだ猫を、生きたまま腹を裂き、仔を取り出す。その仔を乾燥させた物が、魂呑鬼よ。その呪物が年月を経て、自らの意思を持った。それがあいつ」
神代先生の説明に、私は顔をしかめた。
聞くんじゃなかった。
「えと、あの──やっつけたん、ですよね?」
「逃げた」
「逃げた」
黒神由貴と神代先生が、同時に言った。
「手応えはあったけど、とどめは刺せなかった。私が生きているうちに、また巡り会うかどうか。ま、今度会ったら、今度こそぶち殺してやるわ」
道具をくるくるとバトントワリングのように回しながら、神代先生は言った。
くるくると回している様子で、ようやく私はその道具が以前見た独鈷杵だと気づいた。
「みんな怪我はない? じゃあ、ここを出なさい。ここであったこと、あまり人に言うんじゃないわよ。──言っても信じてもらえないだろうけどね」
神代先生は言って、大坪ミキたちをブースの外に連れ出した。
緊張が解けたのか、今になって、大坪ミキたちは泣き始めた。
ブースを出る前に、私は振り向いて、マオタイギが消えた床を見た。
その場所には、何か汚らしい染みができていた。
エピローグ1
数日後。
星龍学園の昼休み、教室に戻ると、黒神由貴が珍しくポータブルCDプレーヤーを聴いていた。
手を伸ばして片方のインナーイヤホンを外し、何を聴いているのか、確かめてみた。
「あん」
黒神由貴が小さく抗議の声を上げた。
流れる曲を数フレーズほど聴いて、私はインナーイヤホンを耳から離した。
「ちょっとくろかみー。これ、大崎豊じゃないの。別にファンでもなんでもなかったんでしょー? なんでこんなの聴いてるのよ」
黒神由貴が大崎豊のCDを聴くのが悪いというわけではないが、意外だったので、私は訊いた。
「そんなにいい曲なのかなって、興味が湧いて。昨日、渋谷のCDショップに行ったのよ。そしたら、あのときの、あの子たちに会って」
「あの子たちって、大坪ミキたち? ちょっと。また因縁付けられなかった? 何もなかった?」
「ううん、私も、もしあの子たちに会えたらラッキーだなって思っていたから。あの子たちに、大崎豊のCDでおすすめは何がいいかって訊いたの」
「へ」
「そしたら、『やっぱりベスト盤でしょ』とか『やっぱり原点はファーストCDじゃない?』とか、いろいろ考えてくれて。すっごく助かった」
たぶん黒神由貴は、あの日の騒動などなかったかのように大坪ミキたちに声をかけ、「素」で大崎豊のおすすめCDを訊いたのだろう。大坪ミキたちも毒気を抜かれ、黒神由貴におすすめを考えてやったのだろう。
こういうのを人徳と言うのだろうか。
再びインナーイヤホンを装着した黒神由貴の口から、小さくハミングがこぼれた。
大崎豊の大ヒット曲、「夜を突っ走れ」だった。
エピローグ2
大好きだったアイドルが死んだ。
単なるグルーピーにすぎなかったかもしれないが、本当に好きだった。
あまりにも悲しみが大きいと、涙も出ない。
「お話し」だと思っていたが、いざ自分がそういう立場になってみると、本当だとわかった。
人に言っても、笑われるに決まっているだろうが、死んでもいいぐらい、好きだったのだ。
CDショップに行くと、追悼特集をやっている。
そんなことで儲けようとするCD屋にむかついたりもするが、やはり、店頭に貼られたポスターを見ると、また涙ぐんでしまう。
「ファンだったの?」
ふと、背後から声をかけられた。
振り向くと、私と同年代ぐらいの女の子がいた。
スレンダーで、これといって特徴のない顔立ちだ。
「会わせてあげようか」
その子は言って、ニヤリと笑った。