
9.黄泉の世界の主
デブ。
そこにいた男性をひと言で言えば、そうなる。
身長は黒神由貴ぐらいで小柄、縦にしても横にしても、前から見ても横から見ても、立っていても寝ていても同じぐらいの、肩に首がめり込んだ、ガスタンクのような体型。顔は上下につぶれた球形で、目は鉛筆で線を一本引いたように細く、髪の毛は干からびたワカメのようだった。
そして、ここ重要。
私は、このデブに見覚えがあった。
何年か前、兄貴の大学の学園祭に行ったとき──
「君たちは、どうやってここにエンターしたんだい? この世界で自由に動き回れるなんて、驚きだよ」
デブは、ぬめぬめとした唇に薄ら笑いを浮かべながら、私たちの方へ歩いてきた。気持ち悪いことこの上ない。
「『黄泉への扉』から来てくれたんだろう? だったら歓迎するよ。大切なお客様さ」
「あなたが秋山さんですか」
黒神由貴が言うと、デブは目を見開いた。と言っても、鉛筆線一本分が三本分ぐらいになった程度だ。
「驚いたね。どうして僕のことを知っているんだい?」
「真理子のお兄さんから聞きました」
「真理子──?」
デブ──秋山は、不思議そうな顔をして、私を見た。しばらく考えて、はたと思い出したような表情になった。
「どこかで見たような気がしたと思ったら……そうか、君は榊の妹だね?」
「そーよ。覚えててくれても、全然うれしくないけど」
私は言った。兄貴の話を聞いたとき、名前を聞いても全く思い出さなかったが、今ここで秋山の容姿を見て、一発で思い出した。
なんというか、インターネットにのめり込んだヲタク趣味の、運動不足でふくれあがった肥満体という、絵に描いたようなタイプだったのだ。印象に残るというのを通り越して、脳に焼き付いていると言ってもよかった。
「学園祭で会ったよね。あのときは、もう少し背が低かったけれど。僕のことを覚えてる?」
秋山はにやにや笑いながら言った。
「忘れるわけないでしょ。私の胸とか足とか、やらしい目でじろじろ見てたじゃない。バレてないとでも思ってたの。変態」
私は言った。状況を考えればもう少し穏やかな言い方をするべきだったかも知れないが、どうにも嫌悪感が先に立った。
秋山のこめかみあたりが、ぴくぴくっと動いた。
「言ってくれるねえ。久しぶりに会った知り合いに、ずいぶんじゃないかい?」
秋山と会話しながら、私は、秋山の話し方に感じる違和感──もっと言うなら、気味悪さにデジャビュを感じていた。
この気味悪さ、二の腕あたりがぞわっとする感じ、何か、覚えがある。
どこで──
思い出した。
テレビのアニメだ。
それと、ここアキバで(この空間ではなく、現実の)耳に入ってくる会話だ。
と言っても、アキバを歩くすべての歩行者の声ではない。
アニメ専門店とか、アニメヲタがよくいる店、そんな店にいるときに、まわりから聞こえてくる、アニメヲタ同士の話し方だ。
具体的に言うなら、まるでアニメの登場人物のような話し方なのだ。
アニメの中でならとくにどうと言うことはないが、日常空間で耳にすると、ものすごく不自然に感じる。
──アニメの登場人物気取りかよ。
私は心の中で毒づいた。
「あんたがこの世界で王様気取りなのは勝手だけど、関係ない人を巻き込むのはやめて。みんな迷惑してんだから」
「おやおや。それはとんだ誤解だね。ここにいるのは、みんな自ら望んでこの世界に来たんだよ? エンターしづらいように、わざわざクロックをいじってあるのに、何度も何度もチャレンジしてさ。それでも、僕のせいだと、君は言うのかな?」
「こういう風になるとわかってれば、誰も来なかったでしょうが」
秋山の物言いにイライラしつつ、私は言った。
「たとえ自分の意志でエンターしたとしても、こんなふぬけ状態になりたかったわけじゃないでしょ。現実の世界に帰してあげなさいよ」
「そもそも、君たちはここに何しに来たんだい? さしずめ、知り合いがここにエンターしたんで、連れ戻しに来たってところかな?」
図星であった。どうすれば酒井美佳や他の人たちを現実の世界に連れ戻せるか、その方法は未だわからないのだが。
「だったら、おあいにくだね。ここに入った人間は、二度と戻れないよ。現実の世界では、昏睡状態のままさ」
「あんたはどうなのよ。あんただって、現実世界では頭に五寸釘突き刺して死んだんじゃん。もうとうに火葬になってんのよ。あんたも戻れないじゃん」
私は言った。痛いところを突いたつもりであった。だが、秋山は平然と言った。
「肉体なんて、どうでもいいんだよ。僕は意識体となって、ネット内だけではなく、黄泉の世界も含めた、霊界の住民となったんだ」
現実の世界で、こんなことを言ったら、100パーセント頭がおかしいと思うところだが、実際に今、自分のアパートで死んだはずのヲタが目の前にいて、話している。
「ここは本当に黄泉の世界なのですか」
黒神由貴が言った。
「もちろんそうさ。──と言っても、電脳空間の中に僕が造った黄泉の世界だけどね」
「で、あなたが造った黄泉の世界で、あなたがここの支配者ということですか」
「そういうことさ。たとえば、ここにいる、ここにエンターした連中の運命は、僕の手中にある」
「え?」
「え?」
私と黒神由貴は同時に言った。
「今ここにいるのは、君たちも含めてすべて意識体だ。生命そのものと言ってもいいかな。だからつまり、ここでの存在がなくなるということは、リアルワールドでの死を意味するんだよ。──試してみようか?」
秋山はイタズラっぽく笑った。(つもりなのだろうが、客観的には気持ち悪い笑いでしかなかった)
秋山は右腕をあげて、近くに立っていた男性の胸にてのひらをあてた。
「デリート」
秋山は言い、ニヤリと笑った。ものすごくいやらしい笑いであった。
秋山がそう言ったとたん、立っていた男性の姿がぶれた。地上波デジタル放送の画像やBSの画像が電波状態が悪くなったときのような、モザイクで分割されたようになったのだ。そして、モザイク模様がみるみる減ってゆき、男性の姿が消えた。
私も黒神由貴も、あっけにとられていた。何が起こったのか、よくわからなかった。

「今、ここにいた人は、リアルワールドで死んだよ」
秋山は私たちを見て、言った。
そんなばかな、と言えなかった。秋山の言っていることはまぎれもない事実だと、あえて言うなら私の本能が告げていた。
「さて、と」
パンパン、とひと仕事終えたと言わんばかりに手をはたき、あたりを見回しながら秋山は言った。
「君たちが探しに来た知り合いも、このあたりにいるんじゃないのかい? あまりうるさくすると、その知り合いも『デリート』しちゃうよ?」
言いながら、秋山はまた別の男性に手を伸ばした。また「デリート」するつもりなのだ。その男性の二人ほど先に、酒井美佳が立っている。秋山がどういう順で「デリート」してゆくつもりかわからないが、このまま「デリート」してゆけば、すぐに酒井美佳が消されることになってしまう。
エゴだとか冷たいとか言われようと、酒井美佳だけは「デリート」させるわけにはいかなかった。
「デリート」
秋山が言うと、秋山の前にいた男性も、さっきのようにモザイク状になって消滅した。
「一応言っておくとね」
秋山は次の人間に──二十歳ぐらいの女性だった──手を伸ばしながら、私たちを見て、言った。
「僕は、君たちも『デリート』できるんだよ。あまり僕を困らせない方がいいと思うね。──デリート」
女性もまた、モザイク状になって、消えた。次が、酒井美佳であった。
この世界、感覚もなく、暑さも寒さも感じないはずなのに、身体中が冷たくなってきて、なのに、頭の芯が熱くなってきた。
「こうやって一人ずつ『デリート』してゆけば、そのうち君たちの知り合いに行き当たるんじゃないかな」
秋山はそう言いながら酒井美佳に近づいてゆき、右手を伸ばした。
「やめろ、ばかっ!!」
思わず私は両手を挙げ、てのひらを秋山に向けて叫んだ。
秋山に向けたてのひらから、白い光がほとばしった。電気のスパークとか雷のようだった。
光はまっすぐに秋山に向かい、身体の中心に命中した。光をまともに受けた秋山は吹っ飛び、ビルの壁に叩きつけられた。
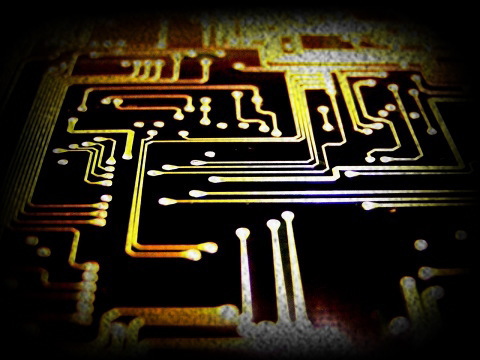
10.電脳空間崩壊
「……!」
「……!」
「……!」
黒神由貴も、秋山も、そしてなにより私自身、唖然とした。
なんだなんだ、なんなんだ、今のは。
私は自分のてのひらをまじまじと見つめた。
別に何も変わりはない。
「……真理子、今のは、どうやったの」
黒神由貴が、目を見開いて言った。さすがに驚いたようだ。いや、それ以上に私が驚いているのだが。
「や、よくわかんない。最近はまってるゲームに出てくる『掌底雷波』って技をイメージしたら、ああなった」
「てめてめてめてめ、おまおまおま、よ、よくもよくも」
ビル壁の前にへたり込んだ状態で、秋山がわめいた。
「お、お、お、おま、なに、なにを」
耳障りなアニメしゃべりをする余裕はないらしく、まともな日本語になっていない。それでも、秋山が驚愕して動揺しているのはよくわかった。まさかこの世界で自分が反撃を食らうとは思ってもいなかったのだろう。
「ゆ、ゆ、許さないぞー。もう許さないぞー。みんな『デリート』してやっからな」
アニメしゃべりをしなくなったら、とたんに幼稚な話し方になった。これが本来の秋山の話し方なのだろう。
秋山はもたもたと立ち上がり、私たちをにらみつけた。
「ソード!」
秋山が右腕を上げてそう叫ぶと、中世の騎士が持つような大振りな剣が手に握られていた。
「もういい! お前らなんか、『デリート』してやるもんか。このソードでぶった切ってやる!」
まるでだだっ子だった。
秋山は剣を両手で構えた。
「くろかみ。危ないから後ろに下がってて」
私は言った。私は秋山と向かい合った状態なので見えてはいなかったが、黒神由貴がその言葉に素直に従うのが、気配でわかった。
こういう状況になった場合、これまでの経験から言えば黒神由貴の方も「真理子が下がってて」と言って私を後ろに下がらせたりするのだが、不思議とそうはならなかった。
秋山の剣幕におびえて、とか、そういうことではないだろうと思った。黒神由貴なりに、何か考えていることがあるのだろう。
私は剣を構える秋山と向かい合い、ほんの少し腰を落とした姿勢を取った。
さっきビルの壁までぶっ飛んだとき、たまたま誰もいない場所だったので、今、秋山が立っているところの周囲には、誰もいない。
私には一つ作戦があった。たぶん、うまくいくはずだ。
「うらああああっ!」
剣を大上段に振り上げ、秋山が奇声を上げた。
──あいつの背後、1メートル!
私は強く念じた。強い加速度を一瞬感じると、目の前に秋山の背中があった。
私はその背中に両てのひらを向け、叫んだ。
「掌底雷波!」
さっきと同じようにてのひらから光がほとばしり、それをまともに背中に受けた秋山は、さっき以上にぶっ飛んだ。
──いける!
──今度はあいつの目の前!
たちまち、私は秋山の真ん前に立っていた。掌底雷波にぶっ飛ばされてフラフラと立ち上がりかけたところに、私は三発目の掌底雷波を見舞った。
「ごぶっ」
車道の、秋山が現れた元々の場所に、秋山は転がった。剣ははるか遠くに飛ばされていた。
この世界において、秋山が受けたダメージがどれほどのものなのかわからなかったが、ここはとことんやっておくべきだろうと、私は思った。徹底的に叩きのめして、この世界に引きずり込まれた人たちを元へ返すのだ。
──あいつのそば!
そう念じて瞬間移動しようと思ったとき、腕をつかまれて、私は「跳べ」なかった。
私の腕をつかんだのは、黒神由貴だった。
「ちょ、なに、放してよ、あのデブぶちのめすんだから!」
私は荒々しく言った。自分では落ち着いていたつもりだが、けっこう興奮していたらしい。
「真理子のおかげで、ここのことがだいたいわかったから、あとは私がやるわ」
私は黒神由貴の顔をまじまじと見た。
「わかったって……ここがどういう世界か、って?」
黒神由貴はうなずき、握っていた私の腕を放して、秋山の方へ歩いて行った。
「気をつけなよ。油断しちゃダメだよ。あのデブ、何するかわかんないんだから」
言いながら、私も黒神由貴に着いていった。
車道に転がり、起き上がろうともがいている秋山から2メートルほどのところで立ち止まって、黒神由貴は秋山に声をかけた。
「秋山さん。ここにいる人たちを元に戻してもらえませんか。こんなことをしたって、なんにもならないでしょう? もうこの世界は消すべきだと思います」
「……やだ」
上半身だけを起こし、黒神由貴と私を憎々しげに見つめて、秋山は言った。
「ここは僕が造った『黄泉の世界』なんだから、僕の好きなようにするんだ」
「……そうですか」
黒神由貴が短く言った。
「ところで秋山さん、この世界を造るのに使ったコンピューターって、かなりのハイスペックマシンなんでしょうね?」
突然、黒神由貴はそんなことを言い出した。いや、今はそんなことはどうでもいいじゃん。
秋山も不思議に思ったらしく、上半身だけを起こした体勢で、「……あ、ああ。まあね」と言った。
「今、世に出ているどんなハイスペックマシンよりも高性能に組んだからな。ある意味、スーパーコンピューターって言っても過言じゃない」
「それだけ高性能だと、ものすごく電気を消費するんでしょうし、熱もすごいんでしょうね」
いやだから、どうしてここで、こんな状況で、パソコン談義が始まるわけ? くろかみ、何考えてる?
「は、そんなことはとっくに対策済みだ」
私のそんな思いをよそに、秋山は得意顔で言った。
「水冷冷却システムを組み込んである。熱暴走なんて、起きっこない」
「へえ……すごいんですね」
本気で感心しているのかいないのか、黒神由貴はそう言った。
「アパートにはそんなものすごいハイスペックマシンは見当たらなかったんですけど、どこかに隠してあるんですか」
あ、黒神由貴はそれを聞き出そうとしていたのか。
「そ。見つからないように、僕がいなくても動き続けるようにしてある。どこにあるかは教えないぞ」
「……秋山さんは、ポテチとかスナック菓子は好きですか」
黒神由貴は、また変なことを言い出した。だから、なんでそんなこと。
「……好きだけど」
さすがに秋山も妙な顔をした。
「もしハイスペックマシンを組み立てながらポテチとかを食べていたら、食べかすがけっこう飛び散ったりしたでしょうね?」
黒神由貴の言葉の意図がわからず、(もちろん私も)秋山はぽかんとした顔で黒神由貴を見つめた。
「マシンをどこに隠してあるか知りませんけど、マシンのまわりや内部にポテチの食べかすが飛び散っていたら、ネズミとかが寄ってきたりしませんか?」
秋山が、「え」という顔をした。
「マシンの配線とか、冷却システムのパイプとか、かじったりしませんか?」
秋山の顔色が変わったような気がした。
「冷却システムに関係する配線だったら冷却システムが停まるでしょうし、パイプをかじられて水が漏れたりしたら、最悪はショートしたりしますよね?」
秋山が、忘れ物を思い出したような顔になった。
バチッ!
突然、どこかでそんな大きな音がして、焦げ臭い臭いが漂ってきた。臭いとか、そんな感覚はここでは感じられないはずなのに。
「ああ、えっ?」
秋山が、きょろきょろとあたりを見回した。私もつられて、同じようにまわりを見る。
パチパチッ、と、そんな音とともに、火花が散った。どこで、というのではなく、何もない空間のあちらこちらで、火花が散っていた。
「……最悪の事態になってしまったみたいですね」
黒神由貴もまわりを見ながら、言った。
「お、おま、おまおまおま、何をした!」
秋山が大声でわめいた。
「何もしていません。ここにいる私が、どうやって秋山さんのハイスペックマシンをどうにかできると言うんですか?」
黒神由貴は、心外なことを言われた、という顔で言った。
いやいやいや、絶対何かしただろう、と、内心で私は思う。
「それよりも秋山さん。あなたはあっちを気にした方がいいと思います」
言いながら、黒神由貴は少し先にあるビルを指さした。私と秋山も、そちらを見た。
──黒神由貴が示したのは、ビルではなかった。
私たちがいる場所から数メートルほど離れたところ、誰もいない、何もないところが、蜃気楼のようにもやもやとかすんでいた。
ん。
私は目をぱちぱちした。
蜃気楼のようにかすむ空間の、その中から、透明でよく見えない何かが現れた。
水槽の中のガラスのかけらのように、よく見えないけれど、なんとなくそこにあるのがわかる、そんな感じ。その何かは、あたりで火花が光ったとき、一瞬だけ輪廓がわかり、どこにいるかがわかった。
蜃気楼のような空間から現れた何かは、一つではなかった。少なくとも三つぐらいはあるように見えた。
あの何かがどんなものかはわからない。わからないが、これだけは間違いないと思った。
あれは、すごく怖いものだ。
あれは、すごく禍々しいものだ。
「……くろかみ、あれって何」
私が小声で黒神由貴に訊くと、黒神由貴も小声で答えた。
「黄泉の世界に棲む妖し。よく見えないでしょ。私も本当の姿はよく知らないの。……真理子。危ないかも知れないから、私の後ろにいて」
あわてて、私は黒神由貴の言葉に素直に従った。
「秋山さん。この世界は、確かにあなたによって創造されたものかも知れませんが、本当の黄泉の世界ともつながっているんです。だから、あそこにいる妖したちが通路を通って、ここに来ているんです。そして──」
黒神由貴は秋山に言った。
「あの妖したちは、必ずしも友好的とは限りません」
黒神由貴に従ったわけではないと思うが、黒神由貴の言葉と同時に、目に見えない妖したちは秋山に向かって行った。
「わ。わわっ、てめこの。来るなっ来るなっ!」
秋山は立ち上がり、虫を追い払うかのように両手を振り回した。妖したちが、秋山の身体にまとわりついたように見えた瞬間、秋山の身体に異変が生じた。
秋山の頭と右腕、それと右胸のあたりが、消滅した。続いて、残る左胸を含む腰から上の部分が消えた。
下半身だけになった秋山は、何かの冗談のようにドタバタと地団駄を踏んでいたが、すぐにその下半身も消えた。
「……何がどうなったの、今」
息を呑んで、私は黒神由貴に言った。
「妖したちが、あの人を黄泉の世界に送り込んだの。あの人が造った世界じゃなく、本当の黄泉の世界に」
「つーと、秋山が成仏したってこと?」
私が訊くと、黒神由貴は首を横に振りながら答えた。
「文字通り、消えたの。あの人の言い方で言えば、あの人の『意識体』は、もうどこにも存在しないの」
「……で、ここはどうなるのかな。まだバチバチ言ってるけど」
私はあたりを見回して言った。バチバチというスパークの音が、さらに大きくなり、火花も、もはや火花と言うにはすさまじくなっていた。竜巻とか台風とかで電柱の電線が切れてスパークしているような、あんな感じだ。目の前にいる黒神由貴と会話するのさえ、そろそろ難しくなってきた。
「ここはもう、消えると思うわ。あ、ほら」
黒神由貴がそう言いながら指さした方を見ると、うつろな顔でたたずんでいた人が、ふっと消えた。
あちらでもこちらでも、次々と消えてゆく。
「あ。あ」
私はキョロキョロとまわりを見ながらそんな声を上げるだけだった。
「たぶん、もうすぐ私たちも同じよう」
言いかけていた黒神由貴が、私の目の前から、消えた。
「ちょっ、くろかみ、え? なにどうなっ」